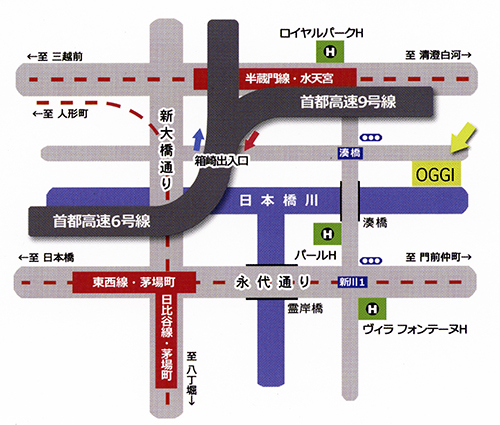中洲の思い出
中洲の思い出 · 2025/09/23
突然始まる、小気味よい三味線の音色。演目「中洲の思い出」の始まりである。三味線の音色に導かれ、翁の唄声がホールの隅々にまで響き渡る。年輪を重ね、渋みを増し、聴く者の心の琴線をふるわす歌声。三味の音色は、翁が紡ぎ出す物語に寄り添い追いかけていく。濃藍(こいあい)の着物に身を包み、その視線は譜面台から離れない。小唄の曲目は江戸時代の日本橋中洲を舞台にした恋物語である。翁自身に、この中洲での思い出や、過ぎ去りし日の甘美な記憶が眠っているのだろうか。中央の三味を弾く女性は、淡い色の着物に身を包み、可憐な花のようだ。無表情に見える。しかしその紡ぎ出すしっとりとした音色は、唄い手の翁の物語に寄り添い、鮮やかに唄の情景を、私たちの耳に、心に、描いて見せてくれる。右側の女性、彼女の三味線を持つ手は、まだ初々しさを残しつも、確かな決意が宿っている。もう一輪の花として魅せ、三味を奏でて二人のセッションを盛り上げている初々しい音色はまた、私たちに別の感動を与えてくれる。三人に交わされる言葉はない。しかし、心を一つにして語られる鮮やか物語それは、私たちを遠い「中洲の思い出」へと誘う、時間旅行でした。